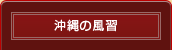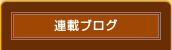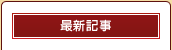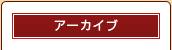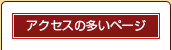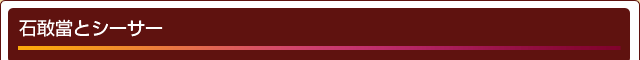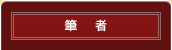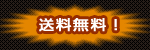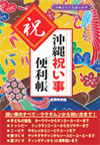年中行事の中の魔よけ その2
シヌグは本島北部に行われている祓いの祭りである。かつては中・南部でも見られたようだが、いつの間にか廃れてしまったようだ。男性が草装神となり、女性や子どもたちを祓うという安田や安波、奥のシヌグがよく知られている。 ユーカビーは、不吉を前もって掌握し、その厄をはずすための行事。シバサシはススキの葉と桑の枝を組合わせてサンをつくり、門や屋敷の四隅などに差し、魔よけとする行事である。 節(シツ)は沖縄本島ではすでに消滅した行事の一つだが、宮古・八重山地方では継承されている。農作物の収穫を感謝し、豊穣を祈 … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
年中行事の中の魔よけ
年中行事の中で魔よけを本旨とする行事としては「シマクサラシ」・「浜下り」・「五月五日」・「ヌーバレー」・「シヌグ」・「ヨーカビー・シバサシ」・「節」・「ムーチー」・「トゥシヌユール」などがある。 シマクサラシでは動物(牛や豚)の生き血をぬりつけた小枝をさす。浜下りでは禊ぎや払いを目的として海水に手足をひたす。 5月5日(グングヮッチグニチ)では邪気を払い、無病息災を叶えるためにあまがしにしょうぶの葉をそなえる。 ヌーバレーは、集落内に徘徊する死霊を追い払うためにエイサーや獅子が集落内を清める。
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
塩
塩がけがれを清める効力があるとして使用されるのは全国共通。力士が勝負前に塩をひとつかみ土俵に投げ入れ清めるのはなじみの風景である。 塩は食物の調理や貯蔵に不可欠であるだけでなく、儀礼にもよく用いられてきた。特に沖縄ではウグヮングトゥにはかかせない。 赤ちゃんの初見せ儀礼には実際に塩の包みを祝いの品としてあげる風習があった。また、その祝い金を「マースデー」と称する。塩によって乳児をけがれから守るという意味がこめられていた。戦後、間もない頃まで盛り塩を火の神のご神体とする地域も多く見られた。 告別式 … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
マブヤーウー、ニンニク
「マブヤーウー」とは幼児の着物につける魔よけの一つである。「マブヤーゲーシ」あるいは「マブイウシー」とよぶ地域もある。 産衣から3~4歳ころまでの着物の後襟下、背縫いの上の方につけてたらす。地域性も見られ、色糸を合わせてたばね、その先端を房のようにたらす、あるいは2~3㎝の正三角形の赤糸で着物の背に縫いつけたところもあったようだ。 ニンニクが邪気を祓うとするのは沖縄だけの風習ではない。その強烈な香気が悪霊どもを近寄らせないと考えられたようだ。 便所にニンニクをさげて魔よけとするのは全島的に見られ … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
ダシチャ、髪の毛
ダシチャ(和名:シマミサオキ)は、沖縄ではその昔から霊力の強い木とされ聖木の一つとされてきた。 弾力性に富むこともあって、楔(くさび)や木釘などにも用いられてきた。またダシチャでつくったグーサン(杖)はハブ除けにもなると信じられている。 髪の毛だが、旅に出るとき姉妹の髪の毛を守り神として持っていく風習はよく知られている沖縄の古俗だが、オナリ神の象徴ともされていたようだ。 古くは魔よけの髪型というのもあり、幼児の髪の一部(うなじのところ)だけを残して残りは剃りあげる。明治・大正期には幼児のこのよう … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
ヒジャイナー
ワラで左綱(ひだりない)にするところからヒジャイナーとよぶ。ヒジャイナーは左手を上に右手を下にして縄を綯ってつくり、通常とは逆になる。 かては生まれた赤子の魂が魔ものにとられないように産室の入口にはり魔よけとした。こうした習俗も失われてしまった。 年中行事の中でも、旧暦の2月の上旬におこなわれる「シマクサラシ」では、ヒジャイナーに牛や豚の骨をつけ、集落に通じる道に張りめぐらし、魔ものの侵入を阻止する習俗が受け継がれている。また御嶽などのイビをヒジャイナーで取り囲んで神域を画する境界としているのが … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
シビランガ(紫微鑾賀) その2
つぎに「紫微鑾賀」である。道教では北極星は天帝(天界にあって万物を支配すると信じられた神)にたとえられて北極大帝と呼称され、天の紫微宮に住んでいるとされている。 墨書きされた文字は、大官と北極大帝が輿に乗って新築する家にやってくるようにという願いをこめたまじないの言葉である。そして、家に嘉利をつけ、家族に幸福をさずけてくださいという家主の心情をあらわすものだったといえよう。 また、米や塩、木炭を昆布で巻いたものを吊り下げるのは、家・屋敷に悪鬼・悪霊などが寄りつかないようにという魔よけである。 〔 … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
シビランガ(紫微鑾賀) その1
建築儀礼の一つに「棟上げ」(ンニアギ)と称される上棟式がある。その際に、棟木に「天官賜福 紫微鑾賀」(テンカンフクヲタマウ シビランガ)あるいは「紫微鑾賀」と墨で書きつける風習があった。地域によっては短冊形の棟札にそれらの字を墨書きし、棟木に打ちつけるところもあったようだ。 棟木や棟札には紅白の紙で包んだ米と塩を対に、真ん中に昆布で巻いた炭を吊り下げた。 文字の意味は、中国人の名前、あるいはすぐれた棟梁や大工などと伝えられ、それが信じられていた、実際はどうだろうか。 まず「天官賜福」の天官とは天 … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
サンとゲーン その2
ゲーンはそのほかに祓い用としても使用される。葬式のときに棺の上に置いたり、墓内を浄化したり、墓内に出入りするときに祓ったり、会葬者などを祓い魔をとり除いたりする。 もっともポピュラーに使用されるのは、旧暦の8月に行われる年中行事の一つ「シバサシ」であろう。屋根や屋敷の門口、軒などにゲーンをさして悪鬼や悪霊の侵入を阻止する。そのときに用いるゲーンは、ススキと聖木の一つである桑の枝を組み合わせてつくる。 マブイグミ(マブヤーグミ)の際に、遊離したマブヤーを囲い込むのもゲーンであり、夜道を歩くときに邪 … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
その他の魔よけ その1 サンとゲーン
サンはわらのシベ(房)や糸芭蕉の葉をひきさいて十字形に結んだもので、煮物や重箱料理などを戸外に持ち出すときに、食べ物のシー(精)を守護するためにその上に乗せる。サンを乗せないとシーが邪気によってうばわれ、腐食しやすいとされている。現在でも祭祀用の供物には小さな手作りのサンを乗せて販売している地域も見られる。 ゲーンはススキの葉を奇数枚をたばねて先を十字形に結んだもので、家や田畑あるいは農作物を守護するために、門口や屋敷、軒、畑などにさしたりする。 数は少なくなったものの、畑の隅にゲーンをさしてい … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない