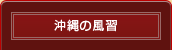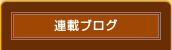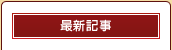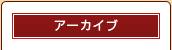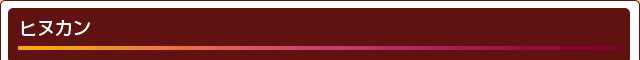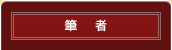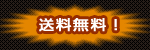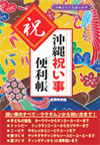ヒヌカンの拝み方
拝み方といえば仰々しく聞こえるが、ふつうの家庭の主婦が拝む場合、特別の作法はない。自分のことばで心よりの祈りをささげる、という一言に尽きるだろう。 神人(カミンチュ)や霊能者(ユタなど)の使う「グイス」(宣〔の〕だてごと)をまねることは全くない。 家族に喜ばしいことがあったとき、祝いごとがあったとき、沖縄の主婦はさして意識もせずヒヌカンとトートーメーの前に居ずまいを正し、そのことを報告し慶事を分かち合う。逆に悲しいことがあったとき、苦境に陥ったときにも、同じようにヒヌカンとトートーメーの前に座して苦しい胸のうちを明かし、救いを求め加護を願う。そんなとき拝みの作法などに気をとられることもない。喜びを分かち合いたい、チムガカイすることを訴えかけたい一心で祈るだけだ。それこそがヒヌカンの拝み方といってもよい。 とはいっても、伝統的なしきたりを軽んじることもない。 代々継承されてきたウグヮンクトゥバ(御願ことば)があれば、それを唱えるにこしたことはない。供物のあれやこれや、線香だのというものがない時代から、ヒヌカンは家の守り神として信仰されてきたのである。 拝みの作法などというものは後世、神人や霊能者によって創作されたものであり、それが伝統となり、継承されてきたにすぎない。だから、拝み方のバイブルなんてものは存在しない。 「御願が通らない」などということを耳にしたことがあるかも知れないが、それは特殊な世界の中で生まれた考え方であり、一般の人がその価値観を共有することもない。