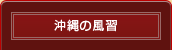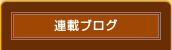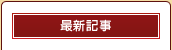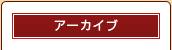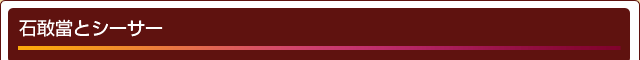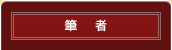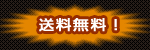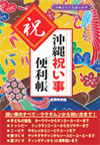貝 その2
貝は地元で「アジケー」と呼称されるシャコガイが多いのだが、6本のトゲが特徴的な「スイジガイ」(水字貝)も見られる。特に玄関に吊した貝はほとんどがスイジガイである。 スイジガイは畜舎の入口やフール(豚便所)の軒先などに吊していたようだが、屋敷内から畜舎が姿を消し、フールもなくなってしまった現在では目にすることもなくなってしまった。畜舎に吊したのは家畜の疫病よけのため、フールに吊したのはフールの神が魔を祓いのける力があると信じられたからであろう。 貝を魔よけとした習俗は全島的に見られたようだが、現在 … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
貝
貝は、家・屋敷に邪悪なものの侵入を防ぐムンヌキムンとして比較的多くの地方で利用されてきたようだが、近年はごく狭い範囲でしか見ることが出来ない。こうした習俗も衰退の一途をたどっているようだ。 伊計島や浜比嘉島の集落の路地をぶらり散策していると、民家の門や屋敷囲いの石垣、ブロック塀の上などに貝の殻を置いた家が目に止まる。 無造作にポンと置かれたものから、セメントなどでしっかり塗り固めたものまで、その設置の仕方は一様ではない。また、石垣の上にズラリと並べた家もあれば、屋敷の四隅に1個ずつ置いた家、屋敷 … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
門柱にすえられた獅子
戦前の伝統的ともいえるやや暗い感じの民家におさらばして、明るくて近代的な住まいに生まれ変わった沖縄の住宅事情。 吉凶にこだわりなく設置される門は、門扉によって固く閉ざされ、よそ者を受け付けないつくりとなっている。そして、どういう理由からか門扉のついた門柱には一対の獅子像をすえる家が多くなった。 コンクリート建築が主流となり、屋根にいられなくなった獅子が、今度は対となって門柱に居場所を見つけたということなのだろうか。居心地は悪くないようにも見える。 屋根獅子が口を開けた「阿形」なのに対し、左右一対 … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
屋根獅子の見すえているもの
年代の古い屋根獅子(今でも古い瓦葺きに見られる)は、目をカッと見開いて恐い形相をしたデザインがほとんどである。「ケーシ」(返し)として殺気ある方向にむけられているのがふつうだ。 従って、屋根獅子が屋根の上から見すえているのは、家・屋敷そしてそこに住む家族に災難をもたらすと考えられていた悪鬼・悪霊など邪悪なものであった。ふりかかる邪悪なものと対峙する屋根獅子が、それらに負けない迫力ある表情をしているのは当然のことだと言えよう。 ところが設置する家がふえるにしたがい、「ヒーゲーシ」や「ヤナカジゲーシ … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
屋根獅子は沖縄発の習俗か?
研究家の一致した見方は、屋根獅子の起源はやはり中国ということだ。そうだからといって、沖縄の獅子文化が「単なるものまね」だということには決してならない。屋根獅子の習俗がこれほどまでに民衆の間に浸透していったのは、それ相応の理由があったからなのであろう。 沖縄ほど魔よけ信仰が庶民生活に深く根をおろした地域は外に見当らない。石敢當・ヒンプン・ゲーンやサン・貝類・ヒジャイナー等々まとめて「ムンヌキムン」と総称される呪物は、すでに沖縄社会の中で定着していたのである。 そのうえで、屋根獅子をムンヌキムンの一 … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
獅子が屋根にのぼったのは?
沖縄民家の象徴ともされている赤瓦屋根(セメント瓦も含む)の上に獅子像を設置する習俗が生まれたのはいつのことだろうか。言うまでもないことだが、獅子が屋根に設置されるための条件として瓦葺きの普及が必須となる。 那覇以外の地方の民家に瓦葺きの禁制が解かれるのは、1889(明治22)年のことである。当然、地方に残る民家の瓦葺きはそれ以降に建築されたものであり、せいぜい百数年しか経っていないということになる。 獅子が地方の民家の屋根の上に設置されるようになるのは、禁制が解かれた1889年以降ということにな … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
石獅子が口を開けるのは何故?
石獅子の多くが口を開けているのは、特別の理由があるからだろうか。 なかでも、ヒーゲーシのために設置された石獅子が口を開けているのは、獅子が火を食べるからだとされている。そのため、獅子像は口を開けヒィーザンとされている山や小高い丘にむけて設置されているのである。 ここで問題なのは「火」の正体である。 ここで言う「火」は文字通りの物が燃える現象ではないし、「ヒィーザン」とは火砕流や火の粉を吹き出す火山のことではない。 火は沖縄人が「ヒーダマ」(火玉)として恐れる死霊のことであり、死霊の正体は女の死霊 … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
ヒーゲーシから守り神へ
村獅子の先がけとなったのは「富盛の大彫石獅子」(旧東風平)、「照屋の石彫獅子」(糸満)、「南風原区の石彫魔除石獅子」(旧大里)の三体だとされている。 富盛の大彫石獅子と照屋の石彫獅子はともに「ヒーゲーシ」や魔よけが目的で設置されたものだということが分かる。しかし、村によっては最高所をわざわざ選んで石獅子を設置したところや複数の石獅子(3体以上も)を設置したところもある。 最高所に設置した石獅子は「ヒーゲーシ」よりむしろ、村内のすべてに目が行き届き、邪悪なものから村人を守護する、いわば「守り神」と … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
シーサーのルーツ その2
墓の袖垣に石筆を立てて、その獅子像を設置するのは中国人の墓制にならったものだとされている。先回紹介した玉陵の東西の石彫獅子の設置は、まさに中国の墓制に倣ったものであろう。また、中国の獅子像は貴族の墓陵や仏寺を守る守護神として設置されているという。 これらのことを考え合わせると、沖縄の獅子像設置の習俗は中国から導入されたものだということが理解できる。 王家を中心とした貴族層に受容された獅子像設置の習俗は、当初は民衆に浸透するまでにはいたらなかったようだ。ただそれは当然のことで、権力とは無縁の一般民 … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない
シーサーのルーツ その1
沖縄人が今日でも愛してやまない「シーサー」を設置する習俗は、残念ながら沖縄が起源となったものではない。 そのルーツをたどる前に、沖縄の古い獅子像を見ていくことにする。 首里城の瑞泉門・歓会門(1470年頃創建)の一対の獅子像、玉陵(1501年頃創建)の東西の彫獅子、末吉道(1456年頃創建)の一対の石獅子、沖縄ようどれの左右一対の石獅子などがよく知られているが、そのうち現存するのが玉陵(一部修復)、末吉宮は一体のみ(博物館)、浦添ようどれは左側の石獅子のみである。 これらの石獅子は、ほとんどは1 … 続きを読む
参考書籍:沖縄の魔よけとまじない