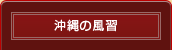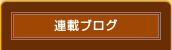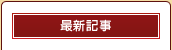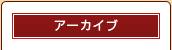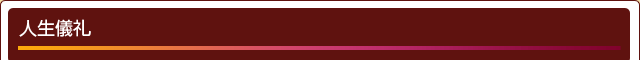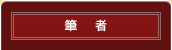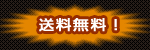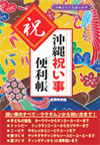ニービチスージ その1
ニービチスージ(祝宴)に入る前に、2つの重要な儀礼が行われる。一つが「ミジムイ」(水盛)で、もう一つが「ユレーウブン」である。 男性家へ到着した花嫁一行は縁側より二番座(仏間)へ招き入れられる。 花嫁は座敷の上座(仏だんにむかって右側)にすわり、対面に花婿がすわる。 二人の前には、ごちそうを盛り、水の入った椀の置かれた膳が用意される。仲立ちの女性が椀の水に右手の中指をひたし、まず花婿の額に3回つけ、それから花嫁の額に同じように3回つける。 水によって二人は浄められることになるというわけだ。これが … 続きを読む
ムクイリ
当日の適当な時間(縁起上満潮時とする地域が多い)にムーク(婿)一行が嫁家へ行く。嫁家に着くとムークジョーイ(付添人)の介添えで酒を盃につぎそれを花嫁の両親に献杯して挨拶をかわす。 その後、火の神に報告(当家の婿となったことを)し、その守護を祈願する。同じように祖霊にも祈願する。 接待をうけて帰着するときに、持参してきたビンシーの酒と水を空にし、当家(嫁家)の酒と水を新しく入れて持ち帰る。持ち帰った水は、その後の「ミジムイ」の儀式に使用する。 それがすむと、嫁迎え(ユミンケー)の儀式が待っている。 … 続きを読む
インジョウジン(結納金)
男性側から女性側へおくる金銭のことをさす言葉とされているが、その語源は明確ではない。現代風にいえば結納金ということになろうか。 表題の「インジョウジン」は旧士族社会で使用されていた言葉で、百姓社会では「ドゥシル」という言葉を使っていたようだ。 インジョウジン(ドゥシルも含む)は多くの地域でクファンムイの席でその金額が決定され、後日ニービチの日取りを決めて女性の側に知らせる際におくったようだ。そのときはニービチスージに使用さする米(ニービチグミ)といっしょにとどけるのが古来からの習わしとなっていた … 続きを読む
妻問い(通い婚)
クファンムイをすませた夜から、男性は女性宅に寝泊まりするようになり、夫婦の契りを結ぶようになる。以後、男性は昼の間の自家の畑仕事などに精を出し、夜ともなれば女性宅へ通うことになる。これが「妻問い」(つまどい)とよばれる通い婚である。ただし、このような風習は平民特有のもので、士族社会にはない。 妻問い期間は地域によって差があり、短いので半年程度、長いものになると子ども2〜3人できるまでという事例もあったようだ。 このような妻問いの風習も大正の初期ごろになると見られなくなり、農漁村でもニービチを終え … 続きを読む
クファンムイ(結納)
サキムイで話がまとまると、つぎの儀礼である「クファンムイ」にすすむ。 クファンムイは、正式に結婚の約束を取り交わす、現代流にいえば「結納」ということになるのだが、女性の家に両家の親戚を招待して小宴をはり、二人を披露するという意味が含まれている。 このようなことから、クファンムイのことを「門中開き」あるいは「一門開き」と称する地域もある。 その日は、男性の家から紅白のもち、カタハラウンブー、サーターアンダギーなどを詰め込んだ重箱二重ねと、八寸重箱を積み上げた料理と酒などを持参し、盃事の後に酒宴とな … 続きを読む
サキムイ
婚約を意味する儀礼のことを「サキムイ」(酒盛り)といい、そのための酒宴のことを「サキムイスージ」という。 結婚相手の娘の親の承諾が得られた時点で、日選びがおこなわれる。日が決まると、男性側の家から本人・両親・親戚の者が連れ立って女性の家へ出向き、盃をくみ交すことになる。この儀礼を「サキムイ」という。地域によって「ニンゴームイ」あるいは「サンゴームイ」とよぶところもある。 サキムイには、男性側から「ニンゴーザキ」(二合酒)、茶、ウチャワキなどを持参する。ウチャワキとしては「クバン」(塩味の天ぷら) … 続きを読む
ニービチ
ニービチとは婚礼のことであり、嫁入りの日を中心とした一連の儀礼の総称である。 婚約祝いの「サキムイ」、結納の「クファンムイ」、婿入りの「ムクイリ」、嫁迎えの「ユミソーイ」、そして結婚祝いの「ニービチスージ」がある。 今でこそ沖縄の結婚式といえば、盛大な披露宴、祝い客の多さ、余興大会もかくやと思わせるほどの数々の出し物等々、まるで有名人かスターの結婚式と見間違うほど華やかなものとして知られているが、かってのニービチはまことに質素なものであった。 種々の儀礼は、それぞれの家庭のナカメーと呼ばれる二番 … 続きを読む
トゥシビー その3
トゥシビーのハイライトは、何といっても「カジマヤー」と称される97歳の生年祝いであろう。 華やかな衣装に身を包んだ当人がオープンカーに乗り、集落内をパレードする。沿道で見送る集落の人びとが手を振り振り祝福しあやかりたいと乞い願う光景はすっかり馴染みとなった。長寿社会となり万余の人びとが百歳を迎える時代になったとはいえ、97歳の齢まで達者でいられたのはやはり果報者といえるだろう。 祝いの席にカジマヤーを飾り、客人はトゥシビーの定番料理でもてなすのだが、桃の漬物と「ルクジュー」と呼ばれるとうふを薄く … 続きを読む
参考書籍:家庭でつくる 沖縄行事料理とふるまい料理 沖縄祝い事便利帳
トゥシビー その2
長寿社会の現在では、還暦を迎えたからといって長寿を祝うという雰囲気はあまり見られない。一つの節目として家族で内祝いをするか、同窓会を兼ねた合同祝いをするのがせいぜいであろう。それも当然のことで、60〜70代になっても気力・体力ともに充実し、やる気の横溢した人が多い。そんな彼らを長寿者として祝う風潮が社会の中から徐々に消えていくのは当り前の話だ。 長寿を祝うのなら「ハチジューグヌユーエー」(85歳)以降ということになろう。ハチジューグヌユーエーは、沖縄本来の生まれ年を祝う「トゥシビー」である。とこ … 続きを読む
参考書籍:家庭でつくる 沖縄行事料理とふるまい料理 沖縄祝い事便利帳